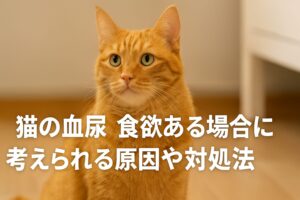猫の甲状腺機能亢進症は、高齢の猫に多く見られる内分泌疾患で、フードの選び方が体調管理に大きく影響します。とくに甲状腺ホルモンの合成に関わるヨウ素の摂取量には注意が必要で、療法食や市販フードの成分にも目を向けることが大切です。
魚系缶詰や海藻類、炭水化物が多いフードはリスクとなる可能性があり、腎臓病との関連にも配慮しなければなりません。また、温かいごはんや穀物を避けた手作り食の工夫、食事療法とメルカゾールとの併用バランスなど、細やかな対応が求められます。
この記事では、猫の健康を守るために知っておきたいフード選びのポイントを具体的に解説します。甲状腺機能亢進症の対策に役立つ知識を整理しながら、わかりやすくお伝えします。
1.猫の甲状腺機能亢進症に適したフードの選び方
2.ヨウ素や食材が与える影響と注意点
3.メルカゾールとの併用時の食事管理のコツ
4.食事療法が難しい場合の対策と代替方法
目次
猫の甲状腺機能亢進症フードの基礎知識

・甲状腺ホルモンとヨウ素の基本的な関係
・フードに含まれる注意すべき食材
・魚系缶詰と発症リスクの関連
・食事療法と薬の併用効果と注意点
・療法食だけでの改善が難しい理由
・甲状腺疾患と腎臓病のつながり
甲状腺ホルモンとヨウ素の関係
猫の甲状腺ホルモンは、体の代謝や神経系の働きを支える重要なホルモンです。このホルモンの原料となるのがヨウ素であり、ヨウ素が不足するとホルモンが十分に作られなくなります。一方で、過剰に分泌されると「甲状腺機能亢進症」と呼ばれる状態になります。
猫の場合、ヨウ素の摂取量が直接の原因になることは少なく、主に甲状腺の良性腫瘍が影響してホルモンが過剰に分泌されると考えられています。とはいえ、ヨウ素の供給量が安定していないと、甲状腺に負担がかかる可能性も否定できません。
そのため、猫の健康維持にはヨウ素を含む食事内容に注意し、必要以上に変動しないよう管理することが大切です。
フード選びで注意すべき食材とは
猫の甲状腺機能亢進症に配慮する際、フードに含まれる原材料にも目を向ける必要があります。とくに注意すべきなのは、海藻類や魚介類、だしの素などヨウ素が多く含まれる食材です。
これらの食品は、甲状腺ホルモンの材料となるため、症状がある猫にとっては過剰な刺激となる可能性があります。また、大豆やキャベツ、ブロッコリーなどの「ゴイトロゲン」を含む食品は、甲状腺の働きを阻害することが知られています。
市販のキャットフードの成分表示を確認し、ヨウ素含有量が明記されていない製品は避けるか、獣医師と相談して選びましょう。過度な制限は栄養バランスを損なうおそれがあるため、適切な判断が重要です。
魚系缶詰と病気リスクの関係
魚を主成分とする缶詰フードには、甲状腺機能亢進症のリスクを高める要因がいくつか存在します。その一つが、缶詰の内面に使われるコーティング剤の影響です。
具体的には、アルミ缶の内張りに含まれる「ビスフェノールAジグリシジルエーテル(BADGE)」が中身に移行し、猫の甲状腺に影響を与えるとされています。また、魚介類自体にもヨウ素が多く含まれているため、過剰摂取につながる可能性もあります。
ドライフード中心の猫と比較して、魚缶詰を常食としている猫では、発症率が高いという報告もあります。リスクを下げたい場合は、魚を主原料とする缶詰を避けるか、BPAフリーの製品を選ぶようにしましょう。
食事療法と薬の併用について
猫の甲状腺機能亢進症には、ヨウ素制限の療法食と投薬治療を組み合わせる方法が有効とされています。どちらか一方のみでは症状のコントロールが難しい場合もあるため、併用が推奨されることがあります。
療法食ではホルモンの材料となるヨウ素の摂取量を抑えることで、内因性のホルモン分泌を抑制します。一方、薬はホルモンの合成そのものを阻害するため、比較的即効性があります。
ただし、薬の副作用が出る可能性や、食事管理の徹底が難しいケースもあるため、どちらの方法にもメリットと注意点があります。治療方針は必ず獣医師と相談しながら決めるようにしましょう。
フードだけで改善が難しい理由
療法食による食事管理だけで猫の甲状腺機能亢進症を完全にコントロールすることは、必ずしも簡単ではありません。その理由の一つに、猫が療法食を好まないという問題があります。
ヨウ素を制限した専用フードは、風味や食感が一般的なフードと異なるため、猫によっては食べてくれない場合があります。さらに、療法食以外のおやつや食べ残しを口にすると、せっかくの管理が台無しになる可能性もあります。
また、症状の程度や他の持病が影響して、食事療法だけではホルモン値が正常化しないケースも見られます。そのため、フードだけで対応するのではなく、他の治療との併用が現実的です。
甲状腺疾患と腎臓病の関係性
甲状腺機能亢進症と腎臓病は、密接に関係しています。甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、腎臓の血流量が増え、腎疾患が一時的に隠れてしまうことがあります。
つまり、甲状腺の治療を始めてホルモン値が下がると、それに伴って腎臓への負荷が表面化し、腎機能低下が明らかになるケースがあるのです。このため、治療中には甲状腺だけでなく、腎臓の状態も定期的にモニタリングすることが重要です。
とくに高齢の猫では、甲状腺疾患と腎不全を併発していることが多いため、腎臓ケアを意識したフード選びや血液検査も欠かせません。
猫の甲状腺機能亢進症フードの選び方と対策

・ヨウ素制限食の効果と限界
・メルカゾールとフード併用時の注意点
・食事管理で見落としがちな落とし穴
・炭水化物を控える理由と代替食材
・温かいごはんが消化に与える影響
・市販フードで避けたい成分と選び方
ヨウ素制限食はどこまで有効か
ヨウ素制限食は、猫の甲状腺機能亢進症を管理するために考案された療法食の一種です。甲状腺ホルモンの材料となるヨウ素の摂取を抑えることで、過剰なホルモン分泌を防ぐ効果が期待されます。
研究では、多くの猫が数週間から数か月のあいだにT4値が正常化したと報告されています。ただし、すべての猫に同じ効果があるわけではなく、約1割程度はフードだけでは改善が見られないケースもあるようです。
また、ヨウ素制限が長期的に猫の健康に与える影響については、まだ十分な研究が行われていません。フードの継続的な使用には獣医師の指導が欠かせず、安易な自己判断は避けるべきです。
メルカゾールとフードの相性
メルカゾールは、猫の甲状腺機能亢進症の治療で広く使われている抗甲状腺薬です。この薬はホルモンの合成を阻害し、比較的早く症状を落ち着かせる効果があります。
ただし、ヨウ素制限食とメルカゾールの併用には注意が必要です。フードによるホルモンの抑制と薬の作用が重なることで、T4値が必要以上に下がる可能性があるからです。
過剰なホルモン低下は、逆に甲状腺機能低下症を引き起こすこともあり、体調を崩す原因となります。そのため、両者を併用する場合は、定期的にT4値を測定しながら投与量や食事内容を調整する必要があります。
食事管理の落とし穴と対策法
甲状腺機能亢進症の猫における食事管理は非常に重要ですが、見落としがちな落とし穴もあります。特に問題となるのが、療法食以外のものをうっかり与えてしまうことです。
おやつや人の食事の残りなどに含まれるヨウ素は、わずかな量でもホルモンの制御を妨げる要因になり得ます。フードの効果を確実に得るためには、ヨウ素を含まない食材以外を徹底的に排除しなければなりません。
また、複数の猫を飼っている家庭では、食事が混ざらないように注意が必要です。フードの管理を徹底し、療法食の効果を最大限に発揮できる環境を整えることが改善への近道です。
炭水化物は控えるべき?
猫は本来、肉を中心に栄養を摂取する動物であり、炭水化物の消化が得意ではありません。甲状腺機能亢進症の猫にとっても、炭水化物の多いフードはおすすめできません。
消化不良が慢性化すると、体への負担が増し、ホルモンバランスを崩すきっかけになることも考えられます。さらに、炭水化物中心の食事は栄養バランスが偏りやすく、筋肉量の減少にもつながりやすいのです。
穀物不使用のフードや、肉や魚、卵を中心とした手作り食に切り替えることで、消化機能を整えながら体調をサポートすることができます。ただし、自己判断による手作り食はリスクもあるため、必ず栄養バランスを意識して作ることが必要です。
温かいごはんが効果的な理由
温かいごはんを与えることは、猫の消化機能を助け、栄養の吸収効率を高める効果が期待されます。特に甲状腺機能亢進症では、代謝が過剰に活発になることで体が疲弊しやすいため、消化に優しい食事が望まれます。
冷たいフードは胃腸を冷やしてしまい、消化不良の原因となる場合があります。そのため、療法食であっても少し温めて与えることで、食いつきが良くなり、必要な栄養をしっかり摂れるようになります。
ただし、過度に熱いものを与えると口内を傷つける可能性があるため、適温に調整して提供するよう心がけましょう。
市販フードで気をつけたい成分
市販のキャットフードを選ぶ際には、原材料表示のチェックが欠かせません。特に甲状腺機能亢進症の猫には、ヨウ素を多く含む成分やゴイトロゲン作用のある食材を避ける必要があります。
たとえば、「海藻」「だし」「魚粉」などの記載がある場合は、ヨウ素の含有量が高い可能性があるため注意が必要です。また、「大豆」や「ブロッコリー」などもゴイトロゲンとして知られています。
さらに、BPA(ビスフェノールA)を含む缶詰製品は、ホルモンに悪影響を及ぼす恐れがあるため、パッケージに「BPAフリー」と明記されている製品を選ぶと安心です。総合的に見て、成分の安定性と安全性を重視したフード選びが求められる。

猫の甲状腺機能亢進症に適したフード選びまとめ
- 甲状腺ホルモンはヨウ素から作られるため食事管理が重要
- ヨウ素の摂取量が多すぎても少なすぎても安定しない
- 海藻類や魚粉などヨウ素を多く含む食材は避けるべき
- 魚系缶詰はホルモン異常との関連があるため注意が必要
- メルカゾールとフードを併用する場合はT4値の管理が必要
- 食事療法のみでは改善が難しいケースもある
- ゴイトロゲンを含む野菜や食品も選別が求められる
- 炭水化物中心の食事は代謝異常のリスクを高める
- 温めた食事は消化を助け体調維持に役立つ
- 療法食以外を与えると治療効果が落ちる可能性がある
- 市販フードの成分表示を必ず確認すべき
- 腎臓病との関係もあるため同時に配慮が必要
- 複数の猫を飼っている場合は食事の混入を防ぐ工夫が要る
- BPAフリーのパッケージを選ぶことが望ましい
- 療法食の効果を最大化するには継続と徹底が鍵となる